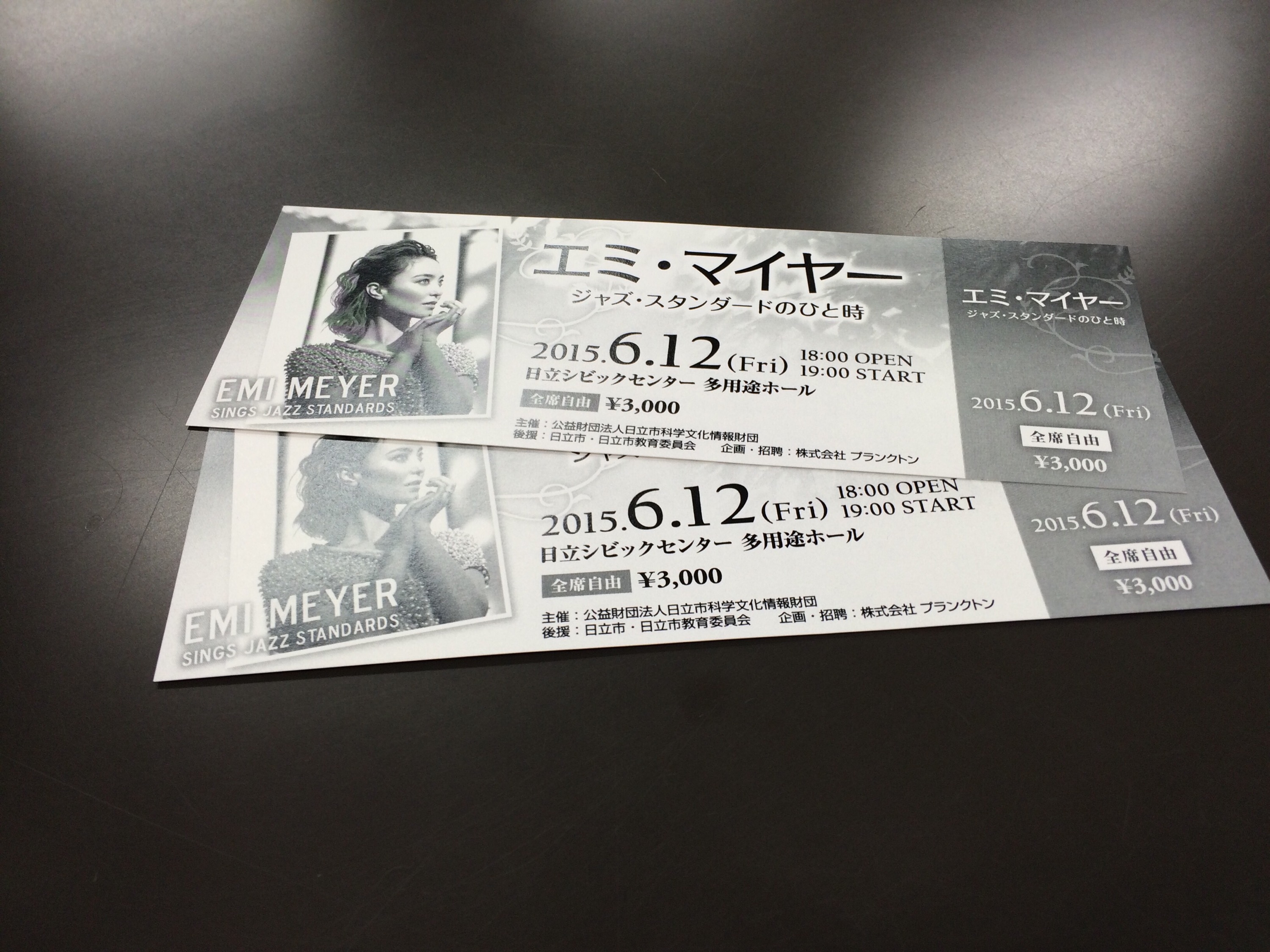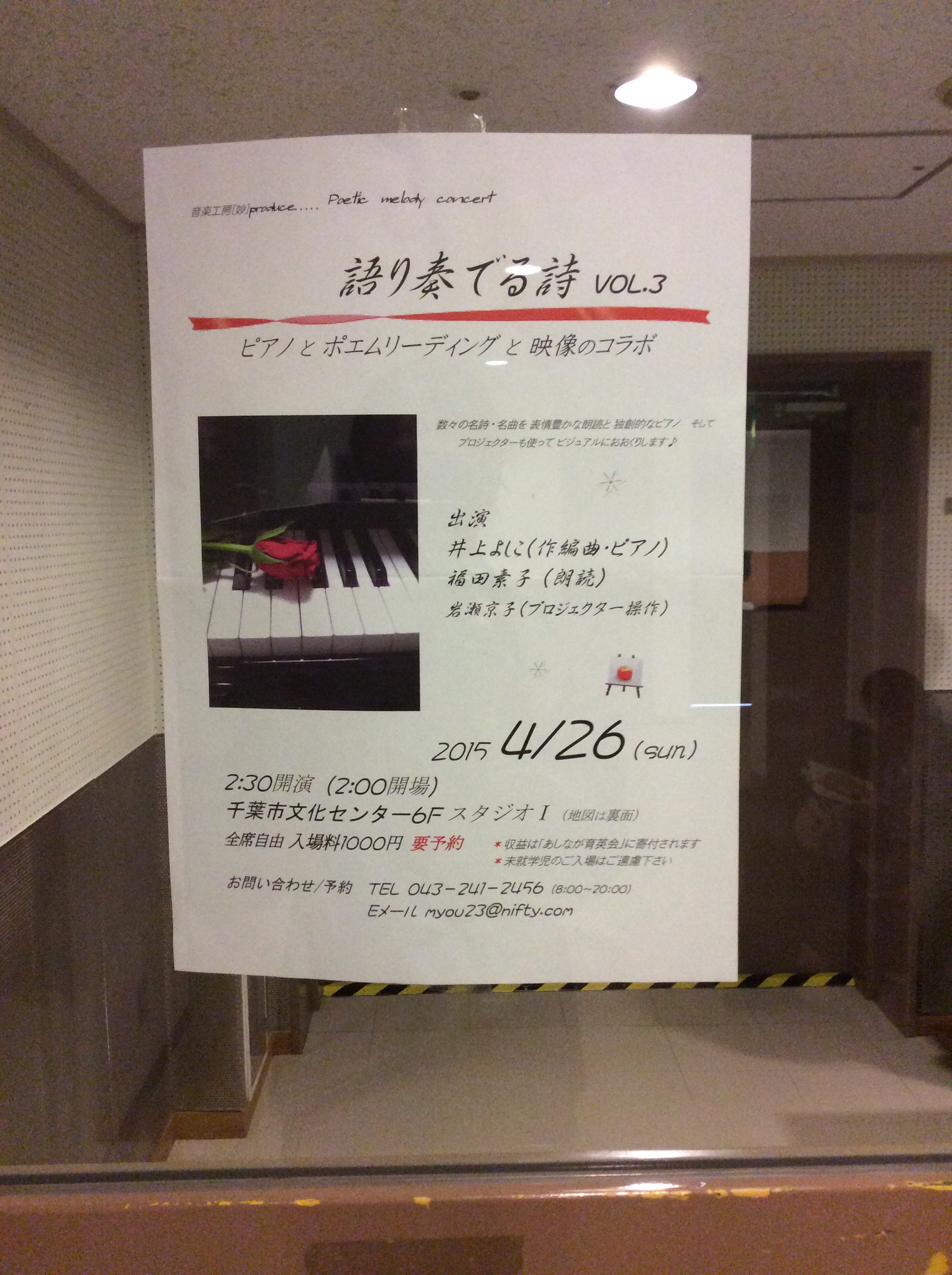仲道郁代さんの「不思議ボール」千葉公演
2011年、10年前からどうしても行きたかったアイルランドを初めて旅することができた。
街の中に音楽が溢れ、劇場文化があり、自然と妖精が生きている街にどうしても自分で行ってみたかった。
完全に素人だけれど、写真を撮り歩きながらダブリンと南アイルランドを旅して歩いた。勝手気ままに。
帰ってきて考え事をしながらちょっとしたウェブサイトっぽいものを作った。
そこに記したのが、「写真を聴いてみよう、音楽を見てみよう」。
数年が経ち、仲道郁代さんに出会い、その考え方に触れた。
「子どもに、大人以上のリスペクトを。」(※1)
と著書に記している仲道さんは、「こどもたちに、音が見えるようになってほしい」とおっしゃっていた。
今、ふと自分が「音楽を見てみよう」と書いた時のことを思い出し、「ははぁ、なるほど。だから僕は仲道さんの考えにすっと入って行けたのかな」と思った。
見えにくくなっていくから、自分が見たい何かを見た証に写真を撮ろう、と思ったその時から、撮った写真は、聴くようにしている。その時の街の音、話し声、風の音。
そして2015年11月、僕の先輩が最終的に実現させてくれた、仲道さんのコンサートに携われる。
約2年かけて進めたプロジェクト。
「不思議ボール」
紙芝居のような映像とともに仲道さんのピアノが物語を紡ぎ、子供たちはもちろん、おとなたちにも語りかける。
音の世界が見えるようになるのか。
どんな世界が見えるんだろう。
ひとりひとり違った景色が見えて、それでいい。
「答えはみんなの胸の中にあるんだよ」と語りかける仲道さん。
このステージを、自分が大切に思う友達に聴いてほしい。
そのお子さんたちにもぜひ聴いてほしい、見てほしい。
公演の情報は↓
http://www.f-cp.jp/info/kouen.php?serial=1783
※1(「ピアニストはおもしろい」仲道郁代 2015 春秋社 p.220)